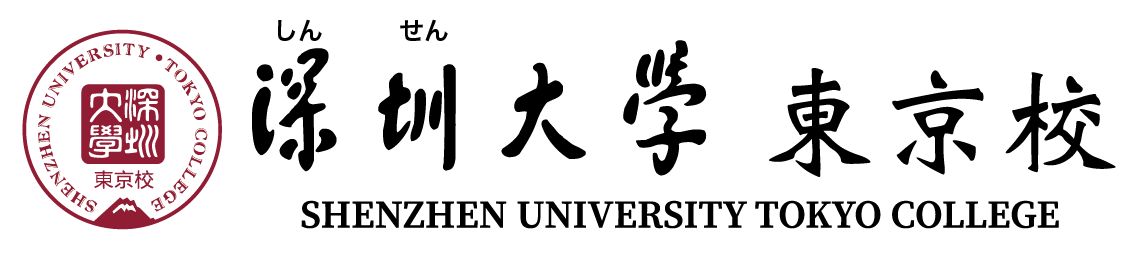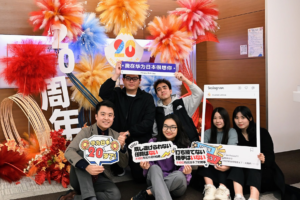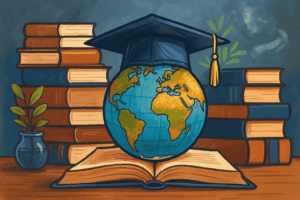近年、中国語学習の需要は高まり続けており、日本の大学では中国語学科や中国語コースを設置する大学が増えています。また、中国の名門大学の日本分校も続々設立されております。
一方、「中国語を学びたいけれど、どんなことが学べるの?」、「将来、中国語を使った仕事はあるの?」とのような疑問を持つ方も多数います。今回は、中国語学習の需要、中国語学科の学習内容、将来の可能性の3点について解説します。
中国語人材の需要が高まりつつある
調査によると、日本における中国語学習の需要は以下のような傾向を示しています。
1.大学での中国語履修者数
文部科学省のデータによると、日本の大学で第二外国語として中国語を履修する学生数は増加傾向にあります。特に、総合大学や国際系の学部では人気が高まっています。
2.HSK(漢語水平考試)の受験者数
HSK日本実施委員会によると、2023年の日本国内のHSK受験者数は約4万人で、過去5年間で20%以上増加しています。特に、ビジネスレベルのHSK5級・6級を受験する社会人が増加傾向にあることが報告されています。
3.訪日中国人観光客の増加
日本政府観光局(JNTO)のデータによると、2023年の訪日中国人観光客数は約250万人で、コロナ前の2019年と比べると回復傾向。
中国語学科の学習内容
中国語学科の分野
一口に中国語学科といっても、その学びの内容は多岐にわたります。一般的には、以下のような分野に分かれています。
- 中国語文学: 中国古典文学や現代文学を研究し、言語の背景や文化を深く理解する。
- ビジネス中国語: 商談、交渉、契約に関する中国語を学び、国際ビジネスでの実践力を養う。
- 中国語教育: 中国語を外国語として教える方法を学び、中国語教師としてのスキルを習得する。
- 翻訳・通訳: プロフェッショナルな通訳・翻訳技術を習得し、国際交流の架け橋となる。
- 国際関係・文化研究: 中国の社会や政治、歴史、文化について学び、グローバルな視点を養う。
- IT・経営との組み合わせ: IT分野や経営学と組み合わせ、中国市場戦略やデータ分析などのスキルを習得する。
このように、中国語学科では多様な分野を学ぶことができ、それぞれの分野が異なるキャリアパスにつながっています。では、具体的にどのようなカリキュラムが組まれているのか、詳しく見ていきましょう。
中国語学科の学習内容
日本の大学における中国語学科のカリキュラムは、主に次のような構成になっています。
- 初級から上級までの中国語授業: 文法、リスニング、スピーキング、ライティングの4技能をバランスよく学ぶ。
- 中国文化・文学・歴史の学習: 言語だけでなく、中国の文化や歴史、現代社会について学ぶ機会が多い。
- 実践的な演習: 中国語でのディスカッションやプレゼンテーション、留学プログラムなど。
- 第二外国語の選択: 英語以外の言語を学ぶ機会がある。
また、日本に設立された中国大学の日本分校では、上記の学習内容に加え、以下のような独自のカリキュラムも取り入れられています。
ビジネス・IT・経営と中国語の融合
グローバル社会においては、語学力に加えて、経営やITの知識も求められます。そのため、これらの分野を組み合わせた実践的なカリキュラムが編成されています。

あわせて読みたい


初参加で3位入賞! 深圳大学東京校の学生、HUAWEI ICT Competitionアジア太平洋決勝にて— 中国語学科…
2025年2月24日、深圳大学東京校の学生3名は、HUAWEI ICT Competition Asia Pacific Finalに出場するため、マレーシアのクアラルンプールへ向かいました。本大会は、HUAW…
地域政策・経済の研究
経済成長が著しい「グレーターベイエリア」(広東・香港・マカオ)の産業構造や経済政策について学び、中国市場でのビジネス機会を深く理解することを目的としています。


中国語学科の将来性
「中国語を学んでも仕事があるの?」と考える方も多いかもしれません。しかし、中国語を学ぶことによるキャリアの選択肢は広がっています。具体的には、以下のような分野で活躍が期待されます。
- 商社やメーカーの海外営業職
- 観光業やホテル業
- 通訳・翻訳業
- 教育機関(中国語教師)
- IT企業の海外事業部
- 中国系企業での勤務(日本企業の現地法人や中国の外資系企業など)
- 国際機関やNGOでの活動
- フリーランスの翻訳・通訳
中国語学科に在籍する学生の中には、在学中にビジネスコンテストに参加したり、中国語を活かして国内外のインターンシップに挑戦する人も増えています。中国語を学ぶことは、単なる語学スキルの習得にとどまらず、ビジネスやテクノロジーの世界で活躍するための大きな武器となるのです。