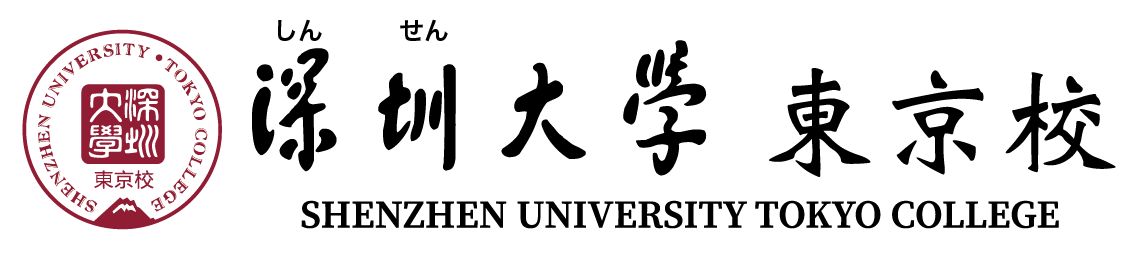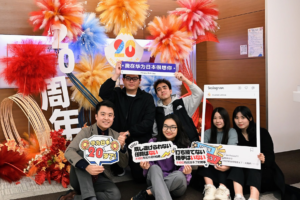日本語と中国語、どちらにも共通して使われているのが「漢字」です。
見た目がそっくりな漢字がたくさんあるので、「中国語って、日本語とほとんど同じなのでは?」と思ってしまう人も多いかもしれません。
でも実は、意味や使い方、さらには形まで違うものもたくさんあります。今回は、そんな「似ているようで違う」中国語と日本語の漢字について、楽しく紹介していきます。
✏️同じ漢字でも、意味がちょっと違う?
たとえば「走る」という字。日本語では「走る=ランニングする」という意味ですが、中国語では「歩く」という意味になります。「走って行くね」と言ったつもりが、中国語では「歩いて行くね」と伝わることになります。
また、「勉強」という言葉も少し意味が異なります。日本語では「学ぶこと」「学習」という前向きなイメージですが、中国語では「努力する」「一生懸命やる」というニュアンスが強く、場面によっては「頑張って無理をする」といった意味で使われることもあるのです。
こうした違いは、文化や言葉の背景が少しずつ違うからこそ生まれるもの。でも、知っておくと「なるほど!」と思える発見ばかりです。

✨形がちょっと違う?簡体字の世界
中国では、日本と違って「簡体字(かんたいじ)」という、画数の少ない漢字が使われています。
たとえば「飛ぶ」は日本語では「飛」と書きますが、中国語では「飞」と書かれます。ほかにも、「図書館」は「图书馆」、「電車」は「电车」となり、どれもすっきりとした形をしています。
簡体字は、読み書きの効率を高めるために作られたもので、中国では日常的に使われています。
一方で、台湾や香港では、日本と似た形の「繁体字(はんたいじ)」が使われていて、地域によっても違いがあるのが面白いところです。
最初は見慣れないかもしれませんが、簡体字を見て「この漢字は何かな?」と考えるのも、中国語を学ぶ楽しさのひとつです。
🗣日本語とちがって、ひらがながない?
日本語では、漢字のほかにひらがなやカタカナを使いますが、中国語にはそういった文字がありません。すべて漢字だけで文を作ります。
たとえば「私は日本に行きたいです」という文は、中国語では「我想去日本」となります。「我」は私、「想」は~したい、「去」は行く、「日本」はそのまま「日本」です。日本語に近い語順なのでわかりやすいですが、ひらがながないぶん、漢字だけで意味をしっかり伝える必要があります。
また、中国語には「ピンイン」というアルファベットの発音表記があり、正しい発音を覚えるときに使います。発音には「声調(せいちょう)」と呼ばれる音の上がり下がりがあって、それによって意味が変わるのも中国語の特徴です。
📘日本人は中国語にちょっと有利?
日本人が中国語を学ぶうえで、実は漢字を知っていることが大きな強みになります。たとえば「図書館」「学校」「空港」など、見ただけでなんとなく意味が想像できる単語も多くあります。
もちろん、意味や発音が少し違う漢字もあるので注意は必要ですが、「まったく知らない言葉」よりも、すでに知っている漢字から意味を推測できるというのは、とても大きなメリットです。
中国語を学びながら、日本語との共通点や違いを発見するのは、本当におもしろい体験です。学校で学ぶだけでなく、看板やメニューなど、身近なところにある中国語を見つけてみるのも楽しいですよ。
✍️まとめ:違いを知ると、もっと面白い!
中国語と日本語の漢字は、見た目は似ていても、それぞれの国で少しずつ違う進化をしてきました。意味が違ったり、形が違ったりする漢字を知ることで、言葉だけでなく文化の違いにも気づくことができます。
「同じ漢字なのに意味が違う!」「簡体字っておもしろい!」
そんな発見を通して、中国語への興味がもっと深まっていくはずです。
これから中国語を勉強する人も、今すでに勉強している人も、ちょっとした違いを楽しみながら、言葉の世界を広げていきましょう!