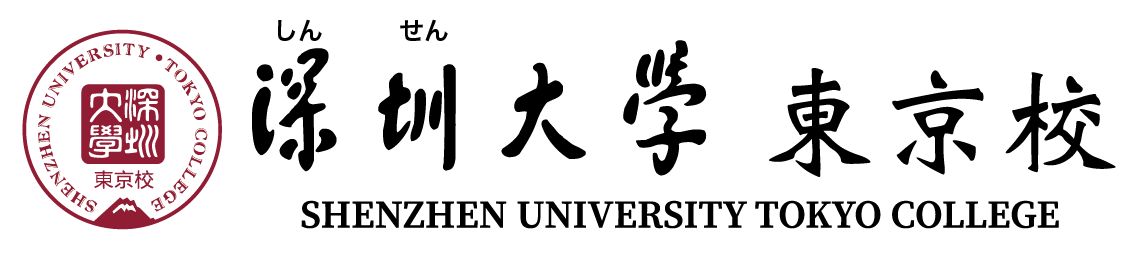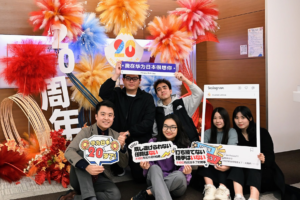いよいよ大学出願の季節がやってきました。高校3年生の皆さん、そして保護者の皆さまにとって、「進路選び」は人生の重要な選択のひとつです。
近年では、語学+ビジネス+ITなどを組み合わせ、国際社会で活躍する力を育てる「グローバル系大学」が注目を集めています。進学情報サイトでも、国際系学部や海外提携型の大学に関する特集が増えており、社会全体の関心が高まっていることが伺えます。
本記事では、出願に向けて知っておきたい準備や心構えを、「書類」「試験」「心の準備」「情報収集」「オープンキャンパス」の5つの視点から解説します。
① 出願書類の準備|ミスを防ぎ、自分らしさを伝えるポイントとは?
大学出願の第一関門は、何といっても提出書類の準備です。期日や記載ミスによるトラブルが意外と多く、保護者が関与することで防げるケースもあります。
主な提出書類(大学により多少異なります)
- 調査書(高校発行)
- 志望理由書
- 自己PR文または活動報告書
- 資格・検定証明書(例:英検、中検、HSK、情報系など)
- 願書(オンラインまたは紙)
★外国大学の日本校へ出願の際は、出願基準や必要書類が一般の日本の大学と異なるため、事前に公式サイトか選抜要項を必ず確認しましょう。また、外国大学の日本校へ出願することにあたって、下記の書類の準備も必要でしょう。
- パスポート(発行するには時間がかかるため、前もって取得することをおすすめ)
- 英語版の調査書・成績証明(高校によって発行不可の場合もあるが、別途翻訳必要)
下記の記事より、深圳大学東京校の出願方法と必要資料を確認できます。」
あわせて読みたい


出願方法と必要資料
出願方法と必要資料 アドミッションポリシー(入学者受け入れ方針) ・ビジネス中国語を習得し、貿易、旅行、製造、起業、ITなど様々な分野でグローバルに活躍した い…
📝 志望理由書は「本人の言葉」で伝えることが鍵
✖ よくあるNGパターン
- ネットの例文かChatGPT生成させた文章をそのままコピペ、または“ありきたりな言い回し”の多用
- 親や先生が代筆・添削しすぎて「誰の言葉か分からない」内容に
✔ 読まれる書類にするには?
- なぜこの大学を選んだのか、「授業内容・先生・留学制度」など具体的な視点で語る
- 将来像とつなげる(例:「中国語+ITを活かして貿易分野で働きたい」など)
- 書いた後、高校の先生に「内容」ではなく「伝わりやすさ」をチェックしてもらう
②試験対策は「体験」から学ぼう|まずはオープンキャンパスへ!
試験準備といっても、何をすれば良いのか迷う人も多いはず。実際、大学の選抜試験、特に総合型選抜では「面接」「小論文」など、学力以外の力も問われます。
こうした対策を進めるうえで強くおすすめしたいのが――
✅オープンキャンパスへの参加です。
オープンキャンパスで得られる試験対策ヒント
- 教職員や在学生と直接話すことで、面接の雰囲気や質問例のヒントが得られる。
- 模擬面接や体験授業を通じて、自分の考え方や伝え方を磨ける。
- 志望理由や自己PRの方向性について、より具体的なイメージが得られる。
出願後のオープンキャンパス参加もおすすめ!
「もう出願したけど、今さら参加しても遅い?」
→ いいえ、むしろ“今”が参加のチャンスです!
出願後に参加するメリット
- 面接前の準備として、大学の雰囲気や試験の傾向をリアルに知ることができる。
- キャンパスの雰囲気や授業の様子を知って、「ここで学びたい」という確信と安心感が得られる。
- 学生スタッフや先生との会話で、入学後の生活をイメージできる。
③心の準備|受験の不安を味方に変えるコツ
受験は、知識や書類だけでは乗り切れない**“心の勝負”でもあります。特に総合型選抜**は、“点数”ではなく“人柄”や“思い”を評価するため、自分の言葉で話す場面が多く、プレッシャーを感じやすいのが特徴です。
そんな中で、どうやってメンタル面を整えていくかが、結果に大きく影響することもあります。
🎓 受験生向け:自信を持てないときは「過去の頑張り」を見直そう
「自分にアピールできるようなことなんてない…」
「志望理由って、何を言えばいいのか分からない…」
こんな風に思っている受験生は決して少なくありません。
でも実は、日々の部活、委員会、友人との人間関係、家族とのやりとり――全部が“あなたらしさ”を表す材料になります。
✅ 面接では完璧な答えより、“その人らしい話し方やエピソード”が評価されることが多いです。
そのためにできること:
- 自分の「過去の頑張りリスト」を作ってみる(学校行事、成功体験、苦労したこと)
- 友達や先生に「自分の長所」を聞いてみる(意外と自分では気づかない強みがある)
👪 保護者向け:子どもを“コーチ”ではなく“応援団”として支える
保護者の方も、子どもが不安そうだったり、試験が近づくにつれてピリピリした様子を見ると、「大丈夫かな?」と心配になるものです。
しかし、受験期においては、「がんばりなさい」よりも「信じてるよ」の方が、子どもの力になります。
- 志望理由の相談に乗るとき、「正解を教える」より「一緒に考える」スタンスで
- 模擬面接の相手をするなら、内容よりも「話し方・表情」をやさしくフィードバック
- 結果に左右されない言葉がけ:「どの道を選んでも応援してるよ」
📝 保護者の“安心感”は、子どもにとって最大の支えです。
心の準備は「等身大の自分を認める」ことから
受験に「理想の自分」は必要ありません。
必要なのは、“今の自分”を丁寧に見つめること、そしてそれを自分の言葉で伝える勇気です。