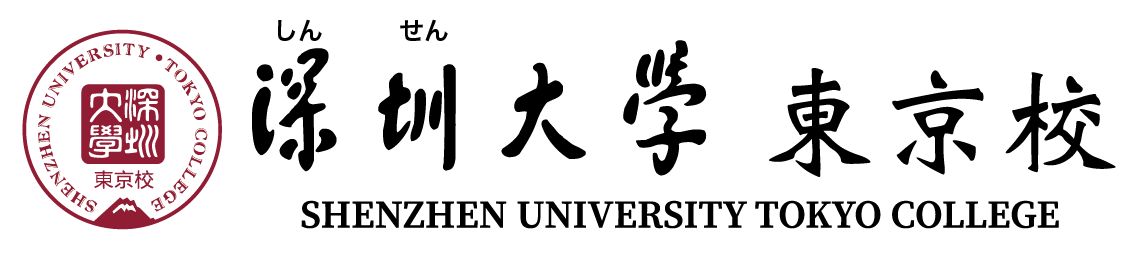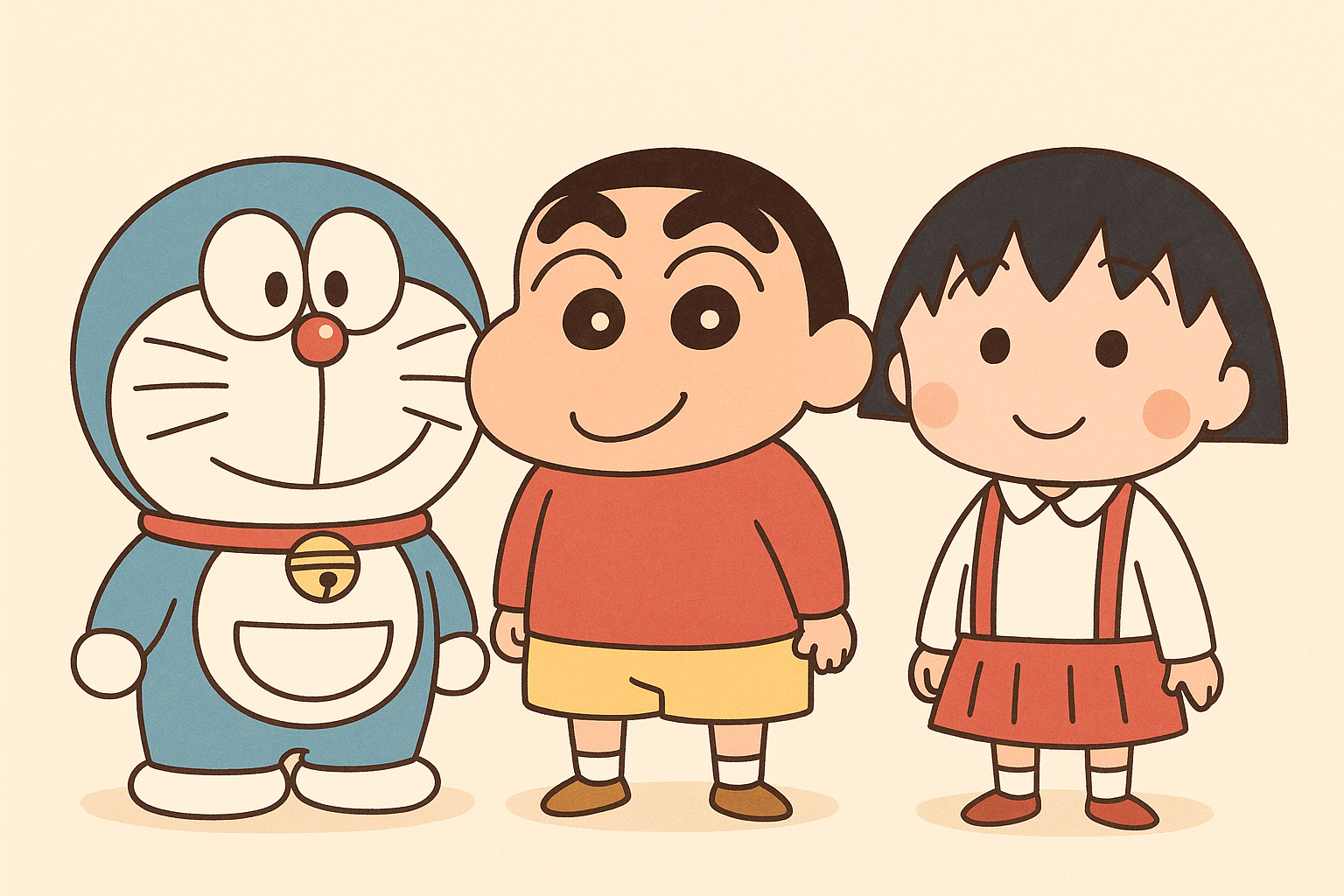こんにちは!今回は、かわいくてちょっとクセになる、日本のキャラクターたちが中国でも大人気になっている理由を紹介します。
日本のアニメ・マンガ文化が世界に広がるなかで、中国の若者たちの間でも「推しキャラ」はとても身近な存在に。
特に最近は、共感性の高い“ゆるかわ系”キャラが熱い注目を集めているんです!
それではさっそく、2025年4月時点で中国のSNSや動画サイトで人気のキャラクターTOP5を紹介していきます!
🥇 第1位:ちいかわ(吉伊卡哇)
吉伊卡哇の名前は、中国語でのかわいらしさと覚えやすさを兼ね備えたものになっていて:
・吉伊(Jí yī) → 音の響きが柔らかく、吉祥(幸運)を連想させる。
・卡哇(kǎ wā) → 日本語の「かわいい=カワイイ」に由来する音訳。
→ つまり、「幸運なカワイイもの」というニュアンスが含まれており、中国人にもポジティブに響く名前なんです。言わずと知れたゆるキャラ界の新星「ちいかわ」こと「ちいさくてかわいいやつ」。
日本ではSNS漫画発からアニメ化、グッズ化と大ブレイクしましたが、実は中国でも爆発的な人気を誇るキャラクターです。
中国では「吉伊(ジーイー)」の愛称で知られ、bilibiliや抖音(TikTok中国版)でちいかわ動画が大量に拡散。ぬいぐるみやステッカー、スマホケースなどのグッズも大ヒットし、上海・北京などのポップアップストアには長蛇の列が!
さらに興味深いのは、中国の若者も「かわいい」だけでなく、ちいかわの“ちょっと切なくてリアルな日常”に共感していること。
「仕事ってつらいよね」「理不尽な世界でもがんばってる感じ、わかる」――そんな声がSNSにあふれていて、日中問わず、現代の若者の心に寄り添うキャラクターとして愛されています。
🥈 第2位:クレヨンしんちゃん(蜡笔小新)
「クレヨンしんちゃん」=日本の国民的アニメですが、中国でも“時代を超えて人気のキャラ”として根強い支持を集めています。
中国では「蜡笔小新(ラービーシャオシン)」の名前で広く知られ、放送から約20年近く経った今もアニメ再放送や映画上映が盛んです。
特に中国の若者たちにとって、しんちゃんはただのギャグキャラではなく、ちょっと変だけど芯のある“理想のこども像”として見られることも。
「大人に媚びない」「自分らしく生きてる」「でも家族思い」というキャラクター性が、どこか自由に憧れる中国Z世代にウケているんですね。
そして2025年夏には、新作映画『超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』が中日同時公開予定ということもあり、しんちゃん人気はますます加速中!

🥉 第3位:ちびまる子ちゃん(小丸子)
「ちびまる子ちゃん」は、中国語で「小丸子(シャオワンズ)」と呼ばれ、昔から親しまれてきた“癒し系代表”キャラです。
中国の地上波で長年放送されていたこともあり、親世代から子どもまで知っている「国民的日常系アニメ」として定着しています。
まる子の「だらけたい」「宿題やりたくない」などの本音全開な性格は、中国の若者にも「わかるわ~」の連発。
学校、友だち、家族とのやりとりなど、“どこにでもあるけど、どこか懐かしい”風景が人気の秘密です。
さらに最近では、まる子のちょっとした名言(例:「明日から本気出す」など)がSNSで画像化・ミーム化されてバズるなど、“令和の共感キャラ”として再注目されています。

🏅 第4位:ドラえもん(哆啦A梦)
「未来から来た猫型ロボット」と言えば、日本だけでなく中国でも圧倒的な知名度を誇る存在――それがドラえもん(哆啦A梦/ドーラーエーモン)です。
中国では1990年代からテレビ放映が始まり、現在に至るまで子どもたちの“初めてのアニメ体験”として親しまれてきました。
特に、どこでもドア・タケコプターなど夢のあるひみつ道具は、国を超えてワクワクを与えてくれます。
最近では、映画『のび太と空の理想郷(ユートピア)』が中国の劇場でも大ヒット。ファミリー層だけでなく、子どものころ観ていた大人が「懐かしい!」とSNSで盛り上がっており、世代を超えて愛され続けています。

🏅 第5位:ポケットモンスター(精灵宝可梦)
最後はやっぱりこの作品、「ポケモン」!中国語では「宝可梦(バオクーモン)」と呼ばれ、ゲーム・アニメ・映画・カードの4メディア展開が全部大人気という最強コンテンツです。
特にピカチュウは「中国の小学生が初めて覚える日本語キャラ」とも言われるほど有名。
最近では、「ポケモンスリープ」や「ポケモンカフェ」などライフスタイルに関わるコンテンツも中国の若者に浸透していて、“かわいい×癒し×健康”という価値観にマッチしているようです。
中国国内では、期間限定のポップアップストアやグッズ販売イベントが毎回大行列。今後は常設ポケモンセンターが登場するという噂もあり、ますます注目の的!
🌸 なぜ日本のキャラクターは中国で人気なの?
① 「かわいい」だけじゃない!キャラの“中身”に共感
日本のキャラクターは、ただ見た目がかわいいだけではなく、ちょっと弱くて、不器用で、それでも一生懸命なところが、多くの中国の若者に刺さっています。
たとえば:
- ちいかわ → 「社会のプレッシャーに疲れた自分みたい」「泣きながら頑張ってる感じがリアルすぎて好き」
- しんちゃん → 「自由奔放だけど、家族思いな一面に泣ける」
実際、中国のSNS「小紅書(RED)」や「微博」では、「ちいかわ=打工人(仕事をしている人)の心の支え(社畜の癒し)」という投稿がバズりました。
② キャラクターが「推し活」にぴったり!
最近の中国Z世代(特に高校生〜大学生)は、「推し活文化」が日本と同じくらい盛ん。
キャラを「アイドル」のように応援したり、グッズを集めたり、カフェでコラボメニューを楽しんだりします。
日本のキャラは:
- デザインが豊富(季節・誕生日・制服verなど)
- グッズが多い(ぬいぐるみ、アクリルスタンド、ポーチ…)
- 世界観がしっかりしてて、“推せる物語”がある
中国でも「ちいかわ × ミニソー(名創優品)」の限定グッズが即完売。「ピカチュウ」や「しんちゃん」のアクリルキーホルダーが若者のカバンについているのは、もはや日常の風景。
③ 日本のアニメ&キャラは“育ってきた文化”の一部
特に1980〜90年代生まれの中国の若者は、「ドラえもん」「しんちゃん」「まる子」で育った世代。
つまり、今大人になっている人たちにとって、日本のキャラは「なつかしさ」「安心感」の象徴なんです。
たとえば中国版Twitter「微博」では、まる子の“さみしいエピソード”をシェアして「泣いた…」「この回覚えてる!」と共感の嵐。
④ 文化や価値観が近く、自然に入り込みやすい
日本と中国は、学校制度や家族構成、社会のルールなどが似ている部分も多く、キャラクターの日常生活が“他人事じゃない”と感じられるのも人気の理由。
- しんちゃんの「保育園」生活
- まる子の「テストで怒られる」
- ドラえもんの「ダメだけどがんばるのび太」
「自分にもそういう時期あったな」「私も怒られて泣いた」みたいな、“わかる~”が国境を越えるんです。
⑤ プラットフォームとマーケティングが強い!
中国では、日本のアニメやキャラクターが正規に見られる&買える環境が整っています。
- bilibili(ビリビリ):中国最大のアニメ配信プラットフォーム。字幕付きで最新話をリアタイ視聴できる。
- 天猫・京東・淘宝など:日本キャラの公式グッズ販売サイト。海外コラボも多い。
- コラボカフェ・イベント・ガチャガチャも増加中!
つまり、「見た→好きになった→買える→推せる」の流れがスムーズなんです。
🎯 まとめ:キャラがつなぐ日中の共感
こうして見てみると、日本で「当たり前に知ってる」キャラクターたちが、国境を超えて中国の人々にも愛されているのって、なんだかすごく嬉しくなりませんか?
たとえば、あなたの隣にいる友達が好きなキャラと、海の向こうの誰かの「推し」が、同じだったりするかもしれません。
“かわいい”って気持ちに、国境なんてないんです。